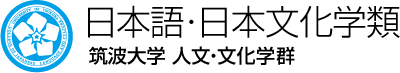2018年冬の入管法改正
-地域社会と多文化共生にとっての示唆-
明石 純一(筑波大学 人文社会系)
1.入管法と日本社会
2018年12月に出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)が改正され、2019年4月に施行されている。入管法やそれに関連する諸政策・制度の主たる対象は外国籍の人々であるから、同法は日本人にとって縁が薄く日常的には意識されにくいかもしれない。しかし入管法の中身や方向性、その展開は、日本社会のあり様に浅からぬ関りをもつ。というのも、外国籍の人々の日本社会における法的地位を含む存在様式に大きな影響を及ぼすと考えられているのが、まさに上述の入管法といえるからである。日本社会を構成するのは、日本国籍を有しなくとも日本に暮らす住民の一人ひとりであり、その数は現在270万人を超えなおも増え続けている 。[1]
21世紀以降、日本に暮らす外国籍住民が減少したのは、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災の影響があった時期に限られる。日本社会、そしてそれを支える経済活動における外国人依存の深まりはもはや不可逆的であるように思える。こうした状況ゆえに、今般の入管法改正には様々な意味が見出せるのではないか。特に本稿では、同改正の位置づけと多文化共生にとっての示唆について私説を記しておきたい。
21世紀以降、日本に暮らす外国籍住民が減少したのは、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災の影響があった時期に限られる。日本社会、そしてそれを支える経済活動における外国人依存の深まりはもはや不可逆的であるように思える。こうした状況ゆえに、今般の入管法改正には様々な意味が見出せるのではないか。特に本稿では、同改正の位置づけと多文化共生にとっての示唆について私説を記しておきたい。
なお、シンポジウム「地域社会と多文化共生」(2019年2月19日)における筆者の報告題目は本稿のタイトルと同じく「2018年冬の入管法改正――地域社会と多文化共生にとっての示唆」であったが、紙幅の制約上、以下では「地域社会」についての議論は割愛する。同様の理由から、本テーマに関する先行研究や理論・学説への言及を省いている。また、次節と次々節の内容については、拙論「二〇一八年入管法改正――その政策的含意について」『三田評論』(1235号:2019年7月)から一部転載し加筆修正している点を、ここにお断りしておきたい。
[1]法務省ウェブサイト「在留外国人統計」(2020年2月7日閲覧)。
2.2018年の入管法改正をどう捉えるか
日本の労働力不足の緩和に資するとされる在留資格「特定技能」の新設を目玉とする2018年の入管法改正については[2] 、同政策分野における歴史的な政策転換と指摘されることが多々ある。同在留資格のもと、14の職種において外国人の雇用が可能となっている。このスキームにより2019年4月より5年間で上限34.5万人を受け入れるが、規模が3万人を超えるのは、介護(6万人)、外食業(5.3万人)、建設(4万人)、ビルクリーニング(3.7万人)、農業(3.65万人)、飲食料品・製造業(3.4万人)といった、いずれも人手不足が深刻とされる産業分野である。
もっともこの制度変更の効果に対しては疑義を差し込む余地がおおいにある。その根拠は、第一に、2018年入管法改正の定量的作用である。この改正が5年間で上限34.5万人の外国人労働者を増加させうることは先に述べた。しかし、その規模は過大とまではいえない。2019年12月時点で就業者数が6,700万人を超える日本の労働市場の規模を考えれば[3] 、この数はあまりに限定的である。もちろん、「特定技能」という受入枠に頼る個別の事業主にとって、それは人材確保のための不可欠なスキームとして活用される。しかし国家経済全体にとってのその効果は局所的なものに留まる。
さらに、2017年10月から翌年10月の1年間で外国人労働者が約18万人増加しているという事実にも目を向けたい[4] 。つまり、「特定技能」を通じて5年間で受入れる労働者の上限数の半分超が、同資格が導入される前の1年間で満たされている。また、2018年10月から2019年10月の1年間に日本で働く外国人は19万人余り増え、全体として約166万人の外国人(在日コリアンを中心とする特別永住者を除く)が就労に従事している [5]。しかしこの間、2019年4月施行の改正入管法により新設された上記の「特定技能」によるものは500人弱に過ぎない。現時点で、同改正は、海外からの労働者の受入れ拡大に直接的に寄与しているとはいえない。
今回の入管法改正は、まぎれもなく重要な転換であるという主張も成立しうる。というのも、日本政府が労働力不足を理由として海外から働き手の受入れを認めたという点で、つまり「フロントドア」を開いたことにおいて、2018年の入管法改正に象徴的な意味を見出せるのである。同改正は、古くは「研修生」、「技能実習生」、「日系人」の就労を認めることで「サイドドア」と久しく揶揄されてきた日本の変則的な外国人労働者政策を、そのすべてではないまでも「正常化」させる一つのプロセスであった。これまで表立って受入れが推進されてこなかった分野において、外国人の雇用が公に認められたことの心理的影響は、可視化できないまでも無視はできない。外国出身の働き手を積極的に登用することが、かつてよりも多くの企業や事業主の前に所与の選択肢として浮上している。
[2]法務省ウェブサイト「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)」(2020年2月7日閲覧)。
[3]総務省ウェブサイト「労働力調査」(2020年2月7日閲覧)。
[4]厚生労働省ウェブサイト「外国人雇用状況の届出状況まとめ」(2020年2月7日閲覧)。
[5]同上。
3.入管法改正と多文化共生
筆者自身は、改正入管法は、制度的な副産物を生み出したのではないかとの私見を持つ。同改正と外国人労働者の増加の実質的な繋がりが見られない現状を踏まえれば、この副産物こそが注視に値する。具体的には、入管法改正と同時期に200億円以上の予算が計上された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(以下、「総合的対応策)が取りまとめられている[6] 。その後も「総合的対応策の充実について」(2019年6月)が決定され、2019年12月には改訂されているように、フォローアップの動きも観察できる。
そもそも、「共生」あるいは「多文化共生」とは何か。多文化共生は、民間による外国人支援のモットーとして1990年代から使われていたが、政策レベルでその言葉が定着し始めたのは、2005年に総務省に設置された「多文化共生の推進に関する研究会」以降である。この研究会は、多文化共生を「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、 地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義した。1990年代の日本における外国籍住民の増加、そしてその一定の割合の定住化という持続的な経験が、上の趣旨を持つ「多文化共生」を正当化する背景事情であった。
そして2006年には「地域における多文化共生推進プラン」が示され、以降も多文化共生の取組みに関する多くの検討が重ねられ、約10年後には、「多文化共生事例集」(2017年3月)が公表されている。ただしこの時点で、日本の多文化共生に関する政府の政策・施策は、今ほどのスケールを備えていなかった。
2018年入管法改正に付随するかのように導入された上述の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」のもとでは、100を超える施策が実施されている。例えば、「多文化共生総合相談ワンストップセンター」の設立にあたり政府から外国人受入環境整備交付金が措置された。また、やはり本改正に合わせて法務省設置法も改正され、法務省の外局として出入国在留管理庁が発足したことにも留意したい。同庁の政策課には外国人施策推進室が新たに設けられているほか、同じく新設の在留管理支援部のもと在留支援課といった部局が開設されています。また、全国8つの地方出入国在留管理局と、3つの支局には、外国人の「受入環境調整担当官」が配置された。現在は、法務省のほか三省庁、すなわち外務省、厚生労働省、経済産業省、そして出入国在留管理庁、東京入管、東京法務局人権擁護部、法テラス外国人部門、東京労働力、ハローワーク、日本貿易振興機構(JETRO)など複数のステークホルダーが関与する「外国人共生センター」の設置も構想されている。
在留資格「特定技能」新設の背景事情のひとつは、周知の通り、技能実習制度のもとでもみられた労働基準法違反の多発や低劣な就労環境、さらには時に失踪へと追い込む労働者搾取に対する一連の批判である。加えて、同制度が規定する家族呼び寄せの禁止や定住阻止の原則への道義的非難も思い出される。いずれも、程度の差こそあれ、入管法改正をめぐる国会審議でも議論され、頻繁にメディアに取り上げられていた。この経緯は、日本の外国人労働者政策、あるいは政府が否定するところの「移民政策」の立案において、上の問題点に対して少なくとも形式上は応答しうる方策やルールを含むことを求めたといえるだろう。
2018年の入管法改正の主眼は、本来的には、必要な期間だけ、必要な職場に、必要な量の労働「力」を確保するということ、それ以上でも以下でもなかったはずである。しかし多方面から長きにわたり数多くの批判と疑義を招き続けてきた技能実習制度の刷新版として、あるいはその延長上に新たな在留資格を設けるうえで、上述の「必要」性だけを前面に押し出し政策立案を進めるのであれば、周囲からの反発と摩擦は収まらず、法改正手続きに支障が生じる。外国から働き手を呼び入れる政策は、一義的にいって国益追求の現れでしかないにしても、かような自国都合主義的な道理を幾分でも中和するためには、制度設計上、ある種のリベラルさや人道性が要請される。この要請は、一種の政治的なバランス感覚として、200億円超の予算措置を伴う「共生」の策へと反映されていったのではないか。
というのは、もちろん筆者の憶測に過ぎず、確たる根拠もない。私見の適否はさておき、測られるべきは、こうした「副産物」が今後の日本社会に及ぼしうる実質的な効果であろう。「総合的対応策」は共生を進めるのか。日本人と外国人の間の相互信頼の強化を促すのか。異なるエスニック集団により多様化が進む社会に対する寛容さを向上させるのか。
4.多文化共生の行方
外国人との共生が日本政府にとってこれまでより優先度が高い政策課題として認識され始めたことは疑いようがない。ただしこうした潮流が、自動的に、望ましい、そして生きやすい社会を実現させるのだろうか。であるとしても、その望ましさや生きやすさははたして誰にとってのものなのか、という問いは残る。別言すれば、多文化共生のかたちはあらかじめ定まっているのではなく、異なる利害や価値観をもつアクター間の交渉や多様なアイデアのすり合わせによって絶えず構築され続ける流動的な類のものではなかろうか。
多文化共生はなるほど多くの人にとって耳当たりがよく、ゆえに様々な団体の活動方針としても用いられている。「移民政策」を否認してきた日本政府にさえ採用された。しかし多文化共生の名のもとで遂行される一部の活動に対して、あるいはその活動の性格について、筆者には懸念がある。筆者自身が関わってきた実践を顧みても、時に内省を余儀なくさせられる。例えば、その「多文化共生」は、文化の異質性をことさら不必要に強調していないか。日本人と外国人の二項対立を先行して成立させ、両者のうちにある文化の多様性への配慮が欠落していないか。多文化共生ならぬ多文化「強制」という本質主義に囚われていないか。名誉感情の罠に陥り、支援と被支援の二元論を維持し強固にしていないか。もちろん一般論として、多文化共生の多くの取組みは善意により着手、推進され、肯定的な作用を生んでいる。そこには有益な助けや建設的なコミュニケーションが確かに存在している。そうであっても日本の多文化共生は上に述べた流動性や二義性を常に内在させているのではないか。
多文化共生は、長らく、その政策的欠如や不備が問題視されてきた。今後否応なく高い関心が寄せられるのは、公に広く承認されるに至った上の規範的理念を拠り所にして講じられる具体的施策の諸影響に対してである。したがって2018年冬の入管法改正は、日本の多文化共生の帰結をその功罪とともに問うていく必要性をわたしたちに再確認させた間接的契機としても、歴史的に位置づけることができるのであろう。
【参考文献】
- 明石純一(2019)「日本における外国人人口の動態と外国人政策の新展開」『統計』70(1)
- 明石純一(2019)「平成30年入管法改正をめぐる一考察:その歴史的意味と「外国人材」受入れのこれから」『法律のひろば』72(4)
- 明石純一(2019)「国境を越える人の移動と移民政策:その影響と課題を考える」『生活協同組合研究』522